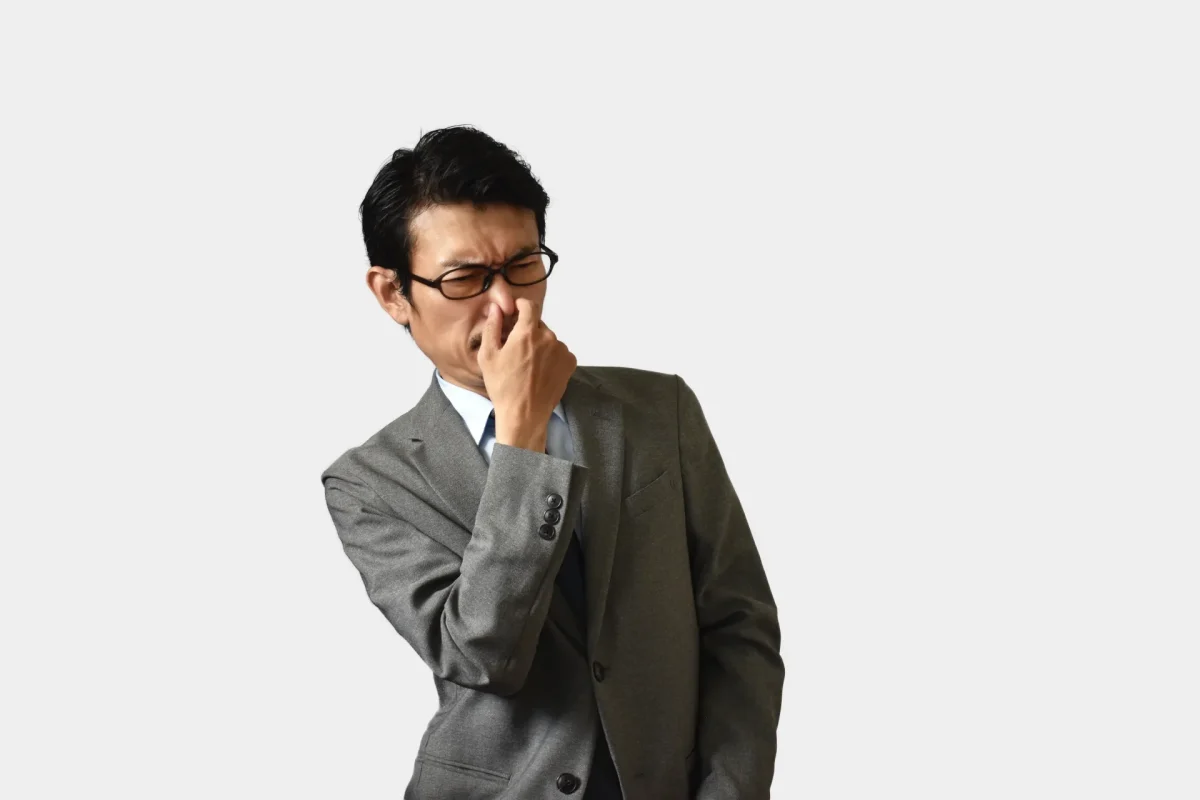風邪をひいた際に「いつもと違う変な匂いがする」「匂いを感じにくくなった」といった経験をされた方は多いのではないでしょうか。
風邪による変な匂いの症状は、鼻づまりによる嗅覚異常や口呼吸による口腔環境の変化、副鼻腔炎などの影響によって生じる可能性があるとされています。
風邪で変な匂いがする現象は比較的よく見られる症状の一つですが、匂いの感じ方や程度には個人差があります。
適切な鼻腔・口腔ケアや生活習慣の改善により症状の軽減が期待できる場合がありますが、症状が長期間続く場合や日常生活に支障をきたす場合には、専門的な判断が重要とされています。
風邪で変な匂いがするのはなぜ?主な原因とメカニズム
風邪で変な匂いがする主な原因は、鼻づまりによる嗅覚機能の低下と副鼻腔炎による分泌物の影響、口呼吸による口腔環境の変化が考えられるとされています。
鼻づまりによる嗅覚異常について、風邪ウイルスによる鼻粘膜の炎症や腫れにより、匂いの分子が嗅上皮に到達しにくくなることで嗅覚が低下します。この状態では正常な匂いを感じられなくなるだけでなく、残存する嗅覚機能により部分的で歪んだ匂いを感じる場合があるとされています。また、鼻腔内の炎症により嗅神経が一時的に機能低下を起こし、普段とは異なる匂いの感覚が生じる可能性もあります。
副鼻腔炎による影響では、風邪に続発して副鼻腔に炎症が生じると、膿性の分泌物が蓄積する場合があります。この分泌物により特有の不快な匂いを感じることがあり、特に朝起きた時や頭を下げた時に強く感じる傾向があるとされています。慢性化すると持続的な匂いの異常として現れる可能性があります。
口呼吸による口腔環境の変化も重要な要因です。鼻づまりにより口呼吸が多くなると、口腔内が乾燥し唾液の分泌が減少します。唾液には口腔内の細菌バランスを保つ重要な役割があるため、唾液分泌の低下により口腔内細菌が増殖し、口臭や口腔内の変な匂いが生じる可能性があるとされています。
風邪による変な匂いの原因は複合的で個人差があるため、症状の現れ方も人によって異なります。
続いて、風邪による匂いの変化の具体的な特徴について見ていきましょう。
風邪による匂いの変化の特徴と症状の現れ方
風邪による匂いの変化は、嗅覚の低下から完全な消失まで様々な程度で現れ、同時に口腔内や鼻腔内からの不快な匂いを感じることが特徴とされています。
嗅覚異常のパターンとして、まず匂いを感じにくくなる「嗅覚減退」から始まることが多いとされています。進行すると匂いを全く感じなくなる「嗅覚脱失」の状態になる場合もあります。また、本来とは異なる匂いを感じる「嗅覚錯誤」や、匂いがないのに変な匂いを感じる「幻嗅」なども報告されています。これらの症状は風邪の経過と共に変化し、回復期には段階的に改善することが一般的です。
自分自身が感じる匂いの変化では、口の中や鼻の奥から金属的な匂い、生臭い匂い、化学的な匂いなどを感じる場合があります。特に朝起きた時や食事前後に強く感じることが多く、歯磨きや鼻をかんだ後に一時的に軽減する傾向があるとされています。また、自分では気づかないが周囲から口臭を指摘される場合もあります。
症状の経過については、風邪の発症と同時期から現れることが多く、鼻づまりの程度と関連して変化する傾向があります。通常は風邪症状の改善と共に数日から2週間程度で回復することが期待されますが、副鼻腔炎を合併した場合には症状が長期化する可能性があるとされています。
風邪による匂いの変化は主観的な症状で個人差が大きいため、適切な判断が重要です。
次に、これらの症状に対する適切な対処法について説明いたします。
風邪で変な匂いがする時の対処法とケアのポイント
風邪で変な匂いがする場合の対処法として、鼻腔と口腔の適切なケア、環境の改善が基本的なアプローチとして重要とされています。
鼻腔ケアの重要性について、鼻づまりの改善により嗅覚機能の回復を促進することが期待されます。生理食塩水での鼻うがいは、鼻腔内の分泌物や炎症物質を除去し、粘膜の状態を改善する効果が期待されるとされています。温かい蒸気の吸入も鼻腔内の血行を促進し、炎症の軽減に役立つ可能性があります。ただし、過度な刺激は避け、優しく行うことが大切です。
口腔ケアの実践では、こまめな歯磨きと舌の清掃により口腔内の細菌バランスを整えることが推奨されます。抗菌作用のあるマウスウォッシュの使用や、唾液分泌を促進するためのガムの咀嚼なども有効な場合があるとされています。十分な水分摂取により口腔内の乾燥を防ぎ、唾液の分泌を促進することも重要です。
環境改善と生活習慣では、室内の適切な湿度を保つことで鼻腔や口腔の乾燥を防ぐことができます。加湿器の使用や濡れタオルの設置などが有効とされています。また、刺激の強い香料や煙草の煙などは嗅覚異常を悪化させる可能性があるため避けることが推奨されます。十分な休息と栄養バランスの取れた食事により、免疫機能を維持し回復を促進することも大切です。
風邪による変な匂いへの対処法は個人の状態により効果が異なるため、適切なケアについてはご相談ください。
続いて、風邪以外で変な匂いがする場合の可能性について見ていきましょう。
風邪以外で変な匂いがする場合の可能性
匂いの異常は風邪以外の様々な原因でも生じる可能性があり、適切な判断のためには他の要因も考慮することが重要とされています。
慢性副鼻腔炎や鼻茸による嗅覚異常では、風邪とは異なり症状が数ヶ月以上持続し、徐々に進行する傾向があります。片側性の鼻づまりや血性鼻汁を伴う場合には、より詳細な検査が必要な場合があるとされています。アレルギー性鼻炎でも季節性や通年性の嗅覚異常が生じる可能性があり、くしゃみや水様鼻汁などの特徴的な症状を伴うことが多いです。
口腔疾患による口臭では、歯周病、虫歯、口腔内感染症などが原因となる場合があります。これらの場合、歯肉の腫れや出血、歯の痛みなどの局所症状を伴うことが特徴とされています。また、胃食道逆流症により胃酸が逆流することで、酸っぱい匂いや口臭が生じる場合もあります。
その他の原因として、頭部外傷による嗅神経の損傷、加齢による嗅覚の自然な低下、薬剤による副作用、糖尿病や腎疾患などの全身疾患に伴う変化なども考えられます。また、精神的ストレスやうつ状態でも嗅覚異常が生じる場合があるとされています。まれに脳腫瘍などの重篤な疾患が原因となる場合もあります。
匂いの異常の原因は多岐にわたるため、風邪症状との関連が不明確な場合や症状が長期間続く場合には専門的な判断が重要です。
最後に、医療機関を受診すべきタイミングについて説明いたします。
匂いの異常で医療機関を受診すべきタイミング
匂いの異常で医療機関への相談を検討すべきタイミングとして、症状の持続期間や程度、他の症状の有無などを総合的に判断することが重要とされています。
早急な受診を検討すべき症状として、突然の完全な嗅覚脱失や、片側のみの症状、血性鼻汁を伴う場合があります。また、頭痛、発熱、視覚異常、意識障害などの神経症状を伴う場合には、より緊急性の高い状態の可能性があるため早めの相談が推奨されます。口腔内の強い痛みや腫れ、持続する口臭なども専門的な評価が必要な場合があります。
継続的な観察が必要なケースでは、風邪症状が改善したにもかかわらず嗅覚異常が2週間以上続く場合や、症状が徐々に悪化している場合があります。日常生活に支障をきたすほどの強い症状がある場合や、食事の味が分からなくなり栄養摂取に影響が出る場合にも相談が推奨されます。
特に注意が必要な方として、高齢者では加齢による変化と病的な変化の区別が困難な場合があるため、変化に気づいた時点で早めにご相談いただくことが大切です。また、既に慢性疾患をお持ちの方や複数の薬を服用されている方では、基礎疾患や薬剤との関連も考慮する必要があります。
匂いの異常についての判断や対処法には個人差があり、適切な対応についてはご相談ください。早期の適切な対応により、原因の特定や症状の改善、生活の質の向上が期待できる場合があります。
※本記事の内容は一般的な情報提供を目的としており、個別の診断や治療に代わるものではありません。症状や治療に関するご相談は、医療機関にご相談ください。
監修医師

略歴
| 2014年10月 | 神戸大学博士課程入学 |
| 2019年3月 | 博士課程卒業医師免許取得 |
| 2019年4月 | 赤穂市民病院 |
| 2021年4月 | 亀田総合病院 |
| 2022年1月 | 新宿アイランド内科クリニック院長 |
| 2023年2月 | いずみホームケアクリニック |