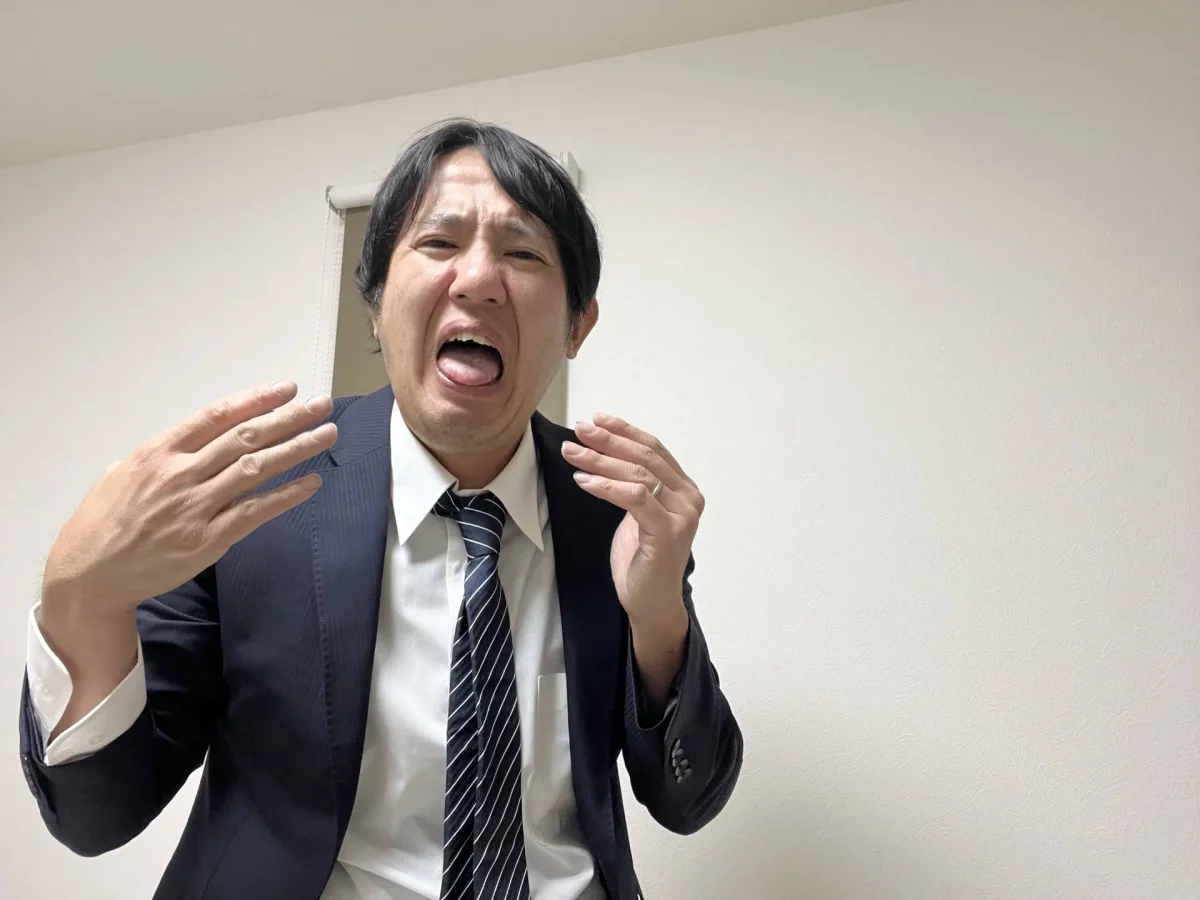風邪をひいた際に「口の中が変な味がする」という経験をされた方は多いのではないでしょうか。
風邪による口の中の変な味は比較的よく見られる症状の一つとされており、その原因や対処法について正しく理解することが重要です。
風邪で口の中に変な味がする症状は、主に鼻づまりや炎症による影響で生じるとされていますが、症状の現れ方や程度には個人差があります。
適切な対処により症状の軽減が期待できる場合がありますが、症状が長期間続く場合や他の気になる症状を伴う場合には、専門的な相談も重要とされています。
風邪で口の中に変な味がするのはなぜ?原因とメカニズム
風邪で口の中に変な味がする主な原因は、鼻づまりによる嗅覚の低下と口腔内や鼻腔内の炎症による影響とされています。
味覚と嗅覚の関係について、私たちが感じる「味」の多くは実際には嗅覚に依存しているとされています。風邪による鼻づまりで嗅覚が低下すると、食べ物本来の風味を感じにくくなり、結果として口の中に変な味や違和感を覚える可能性があります。この現象は「風味障害」とも呼ばれ、風邪の際によく見られる症状の一つとされています。
炎症による影響では、風邪ウイルスによる鼻腔や口腔内の炎症が、味覚を感じる味蕾や嗅覚を感じる嗅上皮に影響を与える可能性があります。また、風邪による鼻水や痰が口腔内に流れ込むことで、苦味や金属味などの不快な味を感じる場合もあるとされています。
口腔内環境の変化も要因の一つとして考えられています。風邪による発熱や口呼吸により口腔内が乾燥すると、唾液の分泌が減少し、口腔内の自浄作用が低下することで変な味を感じやすくなる可能性があります。
風邪による口の中の変な味の原因は複合的で個人差があるため、症状の現れ方も人によって異なります。
続いて、風邪による口の中の変な味の具体的な特徴について見ていきましょう。
風邪による口の中の変な味の特徴と症状
風邪による口の中の変な味は、金属味や苦味、酸味など様々な不快な味として現れることが多いとされています。
よく報告される味の変化として、「金属のような味」「苦い味」「酸っぱい味」「塩辛い味」などがあります。これらの味は食べ物を摂取していない時でも持続的に感じられることが特徴で、特に朝起きた時や空腹時に強く感じる場合が多いとされています。また、普段好きな食べ物の味が変わって感じられたり、味が薄く感じられたりする場合もあります。
症状の現れ方と経過については、風邪の初期から中期にかけて現れることが多く、鼻づまりの程度と関連して変化する傾向があるとされています。症状は数日から1週間程度で改善することが一般的ですが、風邪の症状が長引く場合には味覚異常も継続する可能性があります。
他の風邪症状との関連では、鼻づまり、鼻水、のどの痛み、咳などと同時に現れることが多いとされています。発熱を伴う場合には、口腔内の乾燥により症状がより顕著になる可能性があります。食欲不振や嗅覚の低下を同時に感じる場合も多く、これらの症状は相互に関連していると考えられています。
風邪による口の中の変な味の症状は個人差が大きく、感じ方も人によって異なります。
次に、これらの症状に対する適切な対処法について説明いたします。
風邪で口の中に変な味がする時の対処法
風邪で口の中に変な味がする場合の対処法として、口腔内の清潔保持と適切な水分補給が基本的なケアとして重要とされています。
基本的なケア方法では、こまめなうがいや歯磨きにより口腔内を清潔に保つことが推奨されます。温かい塩水でのうがいは、口腔内の炎症を和らげ、変な味の軽減に役立つ可能性があります。また、十分な水分補給により口腔内の乾燥を防ぎ、唾液の分泌を促進することも重要とされています。
口腔内の清潔保持については、舌ブラシを使用した舌の清掃も効果的な場合があります。風邪による鼻水や痰が口腔内に付着することで変な味の原因となる場合があるため、丁寧な口腔ケアが症状の軽減に役立つ可能性があります。ただし、過度な刺激は炎症を悪化させる可能性があるため、優しく行うことが大切です。
生活上の工夫として、鼻づまりの改善に努めることが重要です。適切な室内の湿度を保つ、温かい飲み物を摂取する、軽い鼻うがいを行うなどにより、鼻づまりが改善されると味覚異常も軽減される可能性があります。刺激の強い食べ物や極端に熱い・冷たい食べ物は避け、消化の良い温かい食事を心がけることも推奨されます。
風邪による口の中の変な味への対処法は個人差があり、効果についても慎重に判断することが重要です。
続いて、風邪以外で口の中に変な味がする場合の可能性について見ていきましょう。
風邪以外で口の中に変な味がする場合の可能性
口の中に変な味がする症状は風邪以外の様々な原因でも生じる可能性があり、適切な判断のためには他の要因も考慮することが重要とされています。
他の疾患による味覚異常として、副鼻腔炎、アレルギー性鼻炎、逆流性食道炎、口腔内疾患などが考えられます。副鼻腔炎では慢性的な鼻づまりや鼻水により、風邪と似た味覚異常が生じる可能性があります。逆流性食道炎では胃酸の逆流により酸っぱい味や苦味を感じる場合があるとされています。歯周病などの口腔内疾患でも、特有の不快な味を感じることがあります。
薬剤による影響も重要な要因の一つです。抗生物質、抗ヒスタミン薬、降圧薬、抗うつ薬など、多くの薬剤が副作用として味覚異常を引き起こす可能性があります。薬の服用開始後に味覚の変化を感じた場合には、薬剤性の味覚異常の可能性も考慮する必要があります。
その他の要因として、亜鉛などの栄養素の欠乏、加齢による味覚の変化、ストレス、喫煙、口腔内の乾燥症候群なども味覚異常の原因となる可能性があります。また、新型コロナウイルス感染症でも味覚・嗅覚異常が報告されており、風邪様症状と合わせて考慮が必要な場合があります。
口の中の変な味の原因は多岐にわたるため、症状が続く場合や他の気になる症状がある場合には専門的な相談が重要です。
最後に、医療機関を受診すべきタイミングについて説明いたします。
口の中の変な味で医療機関を受診すべきタイミング
口の中の変な味の症状で医療機関への相談を検討すべきタイミングとして、症状の持続期間や重症度、他の症状の有無などを総合的に判断することが重要とされています。
受診を検討すべき症状として、風邪の他の症状が改善したにもかかわらず味覚異常が2週間以上続く場合があります。また、味覚異常が徐々に悪化している場合、完全に味を感じなくなった場合、食事が困難になるほど強い症状がある場合なども早めの相談が推奨されます。発熱や激しい頭痛、視覚異常などの他の症状を伴う場合には、より緊急性の高い状態の可能性もあります。
注意が必要なケースとして、高齢者や基礎疾患をお持ちの方、免疫力が低下している方では、軽微な症状でも重篤化するリスクがあるため早めの相談が重要です。また、複数の薬を服用している方では薬剤性の味覚異常の可能性もあるため、専門的な判断が必要な場合があります。
専門的な検査や治療について、味覚異常の原因を特定するために血液検査、画像検査、味覚検査などが行われる場合があります。原因に応じて、薬物療法、栄養指導、口腔ケアの指導などの治療が検討される可能性があります。ただし、治療法や効果については個人差があり、症状や原因によって適切なアプローチは異なります。
口の中の変な味の症状についての判断や対処法には個人差があり、適切な対応についてはご相談ください。早期の適切な対応により、症状の改善や原因の特定が期待できる場合があります。
※本記事の内容は一般的な情報提供を目的としており、個別の診断や治療に代わるものではありません。症状や治療に関するご相談は、医療機関にご相談ください。
監修医師

略歴
| 2014年10月 | 神戸大学博士課程入学 |
| 2019年3月 | 博士課程卒業医師免許取得 |
| 2019年4月 | 赤穂市民病院 |
| 2021年4月 | 亀田総合病院 |
| 2022年1月 | 新宿アイランド内科クリニック院長 |
| 2023年2月 | いずみホームケアクリニック |