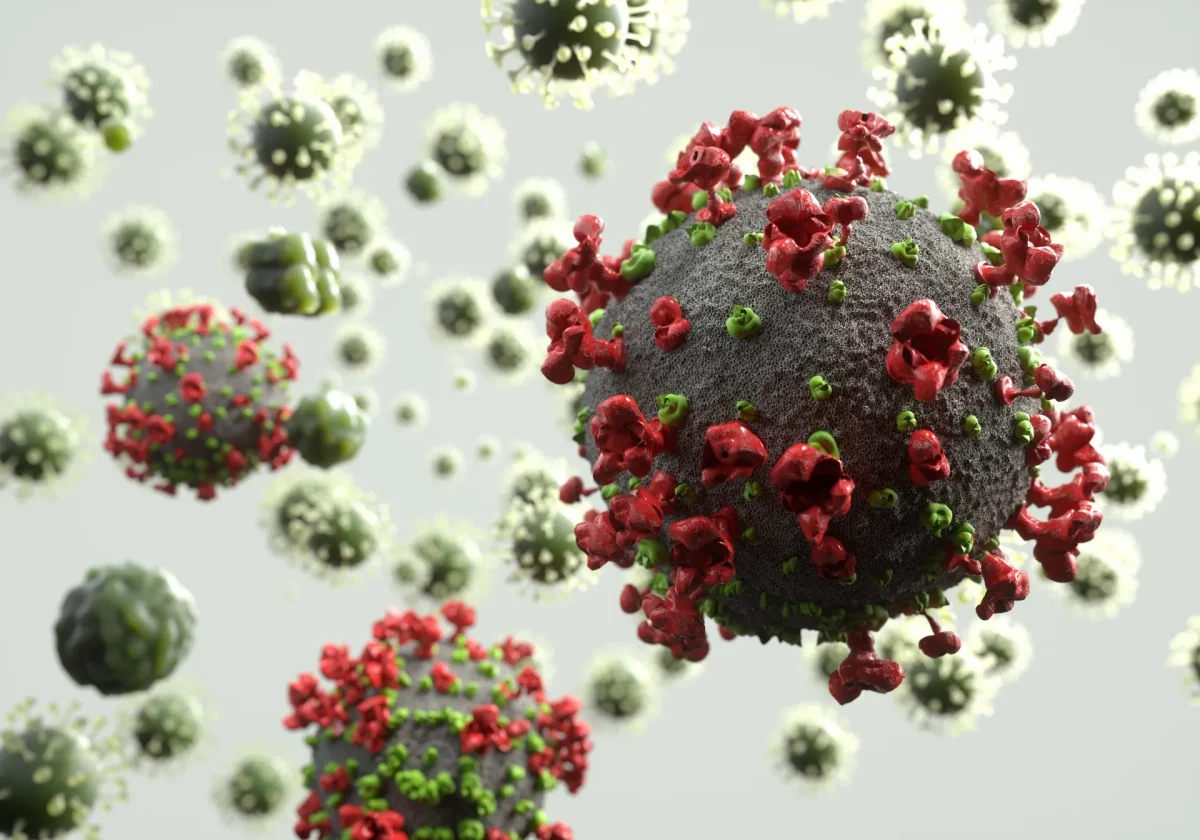風邪のような症状で「細菌性の風邪かもしれない」と考えられる方がいらっしゃるのではないでしょうか。
細菌性の風邪とは、厳密には風邪様症状を呈する細菌感染症を指すことが多く、一般的なウイルス性の風邪とは原因や治療法が大きく異なります。
通常「風邪」と呼ばれる疾患の大部分はウイルス性感染症ですが、細菌による上気道感染症では抗生物質による治療が必要となる場合があるとされています。
ただし、細菌性とウイルス性の感染症の判別は専門的な診断が必要であり、症状だけで自己判断することは困難です。
適切な治療を受けるためには、症状の特徴を理解し、必要に応じて専門的な相談を受けることが重要とされています。
細菌性の風邪とは?ウイルス性風邪との基本的な違い
細菌性の風邪とは、細菌感染による上気道感染症を指すことが多く、一般的なウイルス性風邪とは原因病原体、感染メカニズム、治療法が根本的に異なるとされています。
細菌性とウイルス性の感染メカニズムの違いでは、ウイルス性の風邪は主にライノウイルス、コロナウイルス、インフルエンザウイルスなどが原因となり、ウイルスが細胞内に侵入して増殖することで感染が成立します。一方、細菌性感染症では、黄色ブドウ球菌、溶血性連鎖球菌、肺炎球菌、インフルエンザ菌などの細菌が鼻腔、咽頭、副鼻腔などで増殖することで炎症を引き起こすとされています。細菌は細胞壁を持つ独立した生物であり、ウイルスとは構造や増殖方法が全く異なります。
原因となる主な細菌の種類として、細菌性咽頭炎では溶血性連鎖球菌(A群β溶血性連鎖球菌)が最も代表的な原因菌とされています。細菌性副鼻腔炎では肺炎球菌、インフルエンザ菌、モラクセラ菌などが主要な原因菌となります。急性中耳炎では肺炎球菌やインフルエンザ菌が多く、これらの感染症は「風邪様症状」として現れることがあるため、一般的に「細菌性の風邪」と表現される場合があります。
発症のパターンと特徴では、ウイルス性風邪は通常、徐々に症状が現れて1〜2週間で自然に改善することが多いとされています。細菌性感染症では、急激に症状が悪化したり、初期治療に反応しない場合が多く、抗生物質による治療が必要となります。また、細菌性感染症では局所的な症状(特定の部位の強い痛みや腫れ)が顕著に現れることが多いとされています。
一般的な風邪との関係性として、実際には風邪の90〜95%はウイルス性感染症であり、純粋に細菌が原因となる「風邪」は比較的稀とされています。しかし、ウイルス性風邪の経過中に細菌による二次感染(続発性細菌感染)が起こる場合があり、この場合には抗生物質による治療が必要となることがあります。この状況が「細菌性の風邪」と表現される場合が多いとされています。
細菌性とウイルス性の感染症は基本的に異なる疾患であり、適切な診断と治療法の選択が重要です。
続いて、細菌性風邪の症状の特徴について詳しく見ていきましょう。
細菌性風邪の症状の特徴とウイルス性との見分け方
細菌性風邪の症状は、ウイルス性風邪と比較して局所症状が強く、発熱パターンや分泌物の性状に特徴的な違いがあるとされていますが、症状のみでの確実な判別は困難な場合が多いとされています。
症状の現れ方の違いでは、ウイルス性風邪が全身症状(だるさ、軽度の発熱、鼻水、咳など)から始まることが多いのに対し、細菌性感染症では特定の部位の強い症状から始まることが特徴的とされています。細菌性咽頭炎では激しいのどの痛み、細菌性副鼻腔炎では顔面の痛みや圧迫感が主症状として現れます。また、細菌性感染症では症状の進行が早く、数時間から1日程度で急激に悪化することが多いとされています。
発熱パターンの特徴として、ウイルス性風邪では37〜38℃程度の微熱から中等度の発熱が多いのに対し、細菌性感染症では38.5℃以上の高熱が出現することが多いとされています。細菌性感染症の発熱は持続的で、解熱薬を使用しても下がりにくい傾向があります。また、悪寒戦慄を伴う急激な発熱の立ち上がりも細菌性感染症の特徴の一つとされています。ウイルス性では発熱があっても比較的軽く、自然に解熱することが多いとされています。
鼻水・痰の性状の違いでは、ウイルス性風邪の初期には透明でサラサラした鼻水が出ることが多く、経過と共に粘性が増すことがあります。細菌性感染症では初期から黄色や緑色の膿性の鼻水や痰が出現することが特徴的とされています。副鼻腔炎では粘調で黄緑色の鼻汁、細菌性気管支炎では黄色い痰が代表的な症状です。ただし、ウイルス性感染症でも経過中に色のついた鼻水や痰が出ることがあるため、色だけで判断することは適切ではないとされています。
症状の経過と持続期間では、ウイルス性風邪は通常7〜10日程度で自然に改善傾向を示すのに対し、細菌性感染症では適切な抗生物質治療を行わない限り症状が改善しない、または悪化する傾向があるとされています。細菌性感染症では症状が2週間以上持続したり、一度改善した症状が再び悪化したりする場合が多く見られます。また、合併症(中耳炎、副鼻腔炎、肺炎など)を起こしやすいことも細菌性感染症の特徴とされています。
細菌性とウイルス性の症状には特徴的な違いがありますが、確実な判別には専門的な診断が必要です。
次に、細菌性風邪の治療法について説明いたします。
細菌性風邪の治療法と抗生物質の適切な使用
細菌性風邪の治療では抗生物質の使用が基本となりますが、適切な薬剤の選択と正しい使用方法が重要であり、薬剤耐性を防ぐためにも慎重な判断が必要とされています。
抗生物質治療の必要性では、細菌性感染症に対してはウイルス性風邪と異なり、抗生物質による治療が不可欠とされています。抗生物質は細菌の細胞壁や蛋白質合成を阻害することで細菌を殺菌または増殖を抑制しますが、ウイルスには効果がないため、ウイルス性風邪に対しては使用する意味がありません。細菌性感染症では抗生物質治療により症状の改善、合併症の予防、感染期間の短縮が期待できるとされています。
適切な薬剤選択のポイントとして、原因菌の推定と抗生物質の特性を考慮した選択が重要とされています。細菌性咽頭炎(溶血性連鎖球菌)にはペニシリン系抗生物質が第一選択とされ、副鼻腔炎や中耳炎には広域スペクトラムを持つアモキシシリン・クラブラン酸配合剤などが使用される場合が多いとされています。患者さんのアレルギー歴、腎機能、年齢なども薬剤選択の重要な要因となります。可能な場合には細菌培養検査を行い、原因菌と薬剤感受性を確認することが推奨されます。
治療期間と注意点では、抗生物質は医師の指示通りの期間(通常5〜10日間)、規則正しく服用することが重要とされています。症状が改善しても自己判断で服用を中止せず、処方された薬を最後まで飲み切ることが細菌の完全な除菌と薬剤耐性の予防につながります。服用中に副作用(下痢、皮疹、アレルギー反応など)が現れた場合には速やかに医師に相談することが必要です。抗生物質服用中は腸内細菌にも影響を与えるため、プロバイオティクスの併用が推奨される場合もあります。
薬剤耐性への配慮として、不適切な抗生物質の使用は薬剤耐性菌の出現を促進する可能性があるため、医師の診断に基づく適切な使用が極めて重要とされています。ウイルス性感染症に対する抗生物質の不必要な使用、処方された薬の途中での中止、自己判断での服用などは薬剤耐性の原因となる可能性があります。また、他人への薬の譲渡や以前に処方された抗生物質の再使用も避けるべきとされています。
細菌性風邪の治療では適切な抗生物質使用が重要ですが、正確な診断に基づく治療が前提となります。
続いて、細菌性感染症の検査と診断について見ていきましょう。
細菌性感染症が疑われる場合の検査と診断
細菌性感染症が疑われる場合の診断には、臨床症状の評価に加えて血液検査、細菌培養検査、迅速抗原検査などを組み合わせた総合的な判断が重要とされています。
必要な検査の種類では、血液検査により白血球数やCRP(C反応性蛋白)、プロカルシトニンなどの炎症マーカーを測定することで、細菌感染の可能性を評価できるとされています。細菌感染では白血球数の増加(特に好中球の増加)やCRPの上昇が見られることが多く、ウイルス感染と比較して数値が高くなる傾向があります。迅速抗原検査では、溶血性連鎖球菌咽頭炎の診断に迅速ストレプトコッカス検査が有用とされており、15分程度で結果が得られます。
診断のポイントとして、症状の特徴、身体所見、検査結果を総合的に評価することが重要とされています。細菌性咽頭炎では咽頭の強い発赤・腫脹、扁桃に白苔の付着、頸部リンパ節の腫脹と圧痛が特徴的な所見です。副鼻腔炎では顔面の圧痛、鼻汁の性状、鼻腔内の所見などが診断の手がかりとなります。ただし、これらの所見のみで確定診断を行うことは困難な場合が多く、検査結果との組み合わせによる総合判断が必要とされています。
ウイルス性との鑑別方法では、症状の発症パターン、進行速度、発熱の程度、局所症状の強さなどが重要な鑑別点とされています。ウイルス性感染症では全身症状が主体で、細菌性では局所症状が強いという傾向がありますが、これらの特徴には重複も多く、臨床症状のみでの鑑別は限界があるとされています。検査では、細菌感染でより顕著な炎症反応の上昇が見られることが多いですが、ウイルス感染でも炎症反応が上昇する場合があるため、検査結果の解釈には注意が必要です。
培養検査の意義として、確定診断と適切な抗生物質選択のためには細菌培養検査が最も確実な方法とされています。咽頭培養、鼻汁培養、喀痰培養などにより原因菌を特定し、薬剤感受性試験により最適な抗生物質を選択できます。ただし、培養検査は結果が出るまでに数日を要するため、重篤な症状がある場合には培養結果を待たずに経験的抗生物質治療を開始することが多いとされています。培養結果が判明した時点で、必要に応じて抗生物質の変更を行います。
細菌性感染症の診断には複数の検査を組み合わせた総合的な判断が重要ですが、最終的な判断は専門的な知識が必要です。
最後に、医療機関を受診すべきタイミングについて説明いたします。
細菌性風邪で医療機関を受診すべきタイミング
細菌性風邪で医療機関への相談を検討すべきタイミングとして、症状の重症度や特徴的な所見、症状の経過を総合的に判断し、適切な時期に受診することが重要とされています。
早期受診が必要な症状として、38.5℃以上の高熱が持続する場合、激しいのどの痛みで水分摂取が困難な場合、顔面の強い痛みや腫脹を伴う場合などがあります。呼吸困難、意識レベルの低下、首の硬直などの症状が現れた場合には緊急性が高く、速やかな受診が必要とされています。また、黄色や緑色の膿性の鼻汁や痰が大量に出る場合、血液が混じった鼻汁や痰が出る場合なども、細菌感染の可能性が高いため早期の受診が推奨されます。
抗生物質が必要な場合の判断では、症状が3〜5日経過しても改善しない場合、一度改善した症状が再び悪化した場合、ウイルス性風邪の症状と明らかに異なる特徴がある場合などに抗生物質治療の適応を検討する必要があるとされています。ただし、抗生物質の必要性については医師による専門的な判断が不可欠であり、自己判断での使用は避けることが重要です。市販薬による治療で効果が見られない場合や、症状が日常生活に大きな支障をきたしている場合も受診のタイミングとされています。
合併症のリスクとして、細菌性感染症では適切な治療を行わない場合に重篤な合併症を引き起こす可能性があります。細菌性咽頭炎では扁桃周囲膿瘍、リウマチ熱、糸球体腎炎などの合併症リスクがあり、副鼻腔炎では髄膜炎、脳膿瘍などの中枢神経系合併症の可能性もあるとされています。これらの合併症を予防するためには、適切なタイミングでの診断と治療が極めて重要です。高齢者、糖尿病患者、免疫不全状態の方では合併症のリスクが高いため、より早期の受診が推奨されます。
適切な相談のポイントとして、症状の詳細な経過、発熱のパターン、鼻汁や痰の性状、局所症状の特徴などを医師に正確に伝えることが適切な診断につながります。過去の抗生物質使用歴やアレルギー歴、基礎疾患の有無なども重要な情報となります。また、症状に対する不安や心配が強い場合、適切な治療法について詳しく知りたい場合なども、遠慮なく相談することが重要とされています。薬剤耐性への懸念や抗生物質の副作用について質問することも、安全な治療のために有効です。
細菌性風邪についての判断や対処法には専門的な知識が必要であり、適切な対応についてはご相談ください。早期の適切な診断と治療により、症状の改善と合併症の予防が期待できる場合があります。
※本記事の内容は一般的な情報提供を目的としており、個別の診断や治療に代わるものではありません。症状や治療に関するご相談は、医療機関にご相談ください。
監修医師

略歴
| 2014年10月 | 神戸大学博士課程入学 |
| 2019年3月 | 博士課程卒業医師免許取得 |
| 2019年4月 | 赤穂市民病院 |
| 2021年4月 | 亀田総合病院 |
| 2022年1月 | 新宿アイランド内科クリニック院長 |
| 2023年2月 | いずみホームケアクリニック |